さり気ない一言で、お上から父の命を救った話 森鴎外『最後の一句』
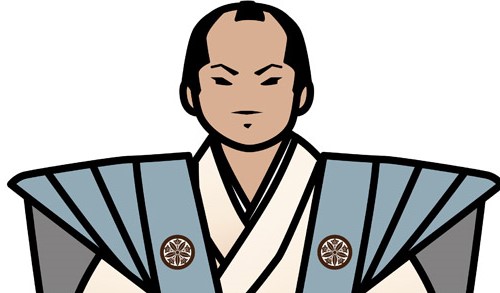
さり気ないが、皮肉めいた言葉を放ち、お上から父を救った話。
その言葉は古今東西を問わず、通ずるものがあろう。
そんな考えが頭をよぎり、森鴎外の「最後の一句」を読み返してみた。
・題名 『最後の一句』
・作者 森鴎外
・発表 大正4年 10月発表(1915年)
・発行 筑摩書房 1992年 ちくま日本文学全集「森鴎外」内
目次
登場人物
・桂屋いち :桂屋太郎兵衛の長女、16歳
・桂屋まつ :桂屋太郎兵衛の二女、14歳
・桂屋長太郎 :桂屋太郎兵衛の養子、12歳
・桂屋とく :桂屋太郎兵衛の三女、 8歳
・桂屋初五郎 :桂屋太郎兵衛の長男、 6歳
・女房 :桂屋太郎兵衛の女房、33歳
・桂屋太郎兵衛 :船乗業、物品横領で死罪の執行待ち
・佐佐又四郎成意:大坂西町奉行
・稲垣種信 :大坂東町奉行 官職「淡路守」
・太田資晴 :大坂城代 官職「備中守」
※備考
現代の「大阪」は、江戸時代「大坂」と表記。
「奉行・城代」とは幕府の役職、「淡路・備中守」とは朝廷の官職。
「関白・太政大臣・征夷大将軍」等は、朝廷の官職。
作品は徳川吉宗の治世だが、上記通りに記せば
徳川吉宗は幕府の役職は「将軍職」、官職は当時「正二位右大臣」。
因みに、初代将軍「徳川家康」は「従一位太政大臣」。
作品概要
元文3年(西暦1738年)11月23日、お上の指示にて、桂屋太郎兵衛を大坂の木津川口で曝した後、斬刑に処すとのお触れが下った。
桂屋太郎兵衛とは2年前迄、船乗業を営んでいたが或る日、船が嵐に遭難。半難破船になり、積み荷の半分を喪失した。
遭難した船は、太郎兵衛が雇っている人間の船。つまり太郎兵衛は雇い主。
使用人は残った積み荷をお金に換え、太郎兵衛の許に戻って来た。
本来なら残った積み荷の代金は、船主の物である。船主に返すのが筋。
しかし魔が差したとでも言うのか、太郎兵衛は雇用人が持ち帰ったお金を折半、懐にいれてしまった。
所謂、ネコババである。船が損壊した事が頭にあったのかもしれない。
処が船主が、その事実を聞きつけ調査。
奉行所に訴えた際、船主の訴えが認められ太郎兵衛はあえなく御用。雇用人は逃走してしまった。
その罪の沙汰が、上記の通りに決まったのである。
確かに厳しい沙汰とも思われるが、当時は米が経済の基本であり、船荷が米で当時「米将軍」と云われた吉宗の治世だった為、とりわけ米については、厳しい処置が取られたのかもしれない。
事件以降、世間を避け、ひっそり暮らしていた桂屋一家の許に、太郎兵衛の女房の実家の母から知らせが来た。
女房は来るべきものが来たと思っていたが、いざ来て持てば何をして良いかわからず、只慌てふためくばかり。
元々裕福そうな家から嫁いで来たと思われる娘なので、いざとなればやはり頼りない。
太郎兵衛と女房は4人の実子、1人の養子の男の子がいた。
年齢で一番上は「いち」、16歳。
二女が「まつ」、14歳。
次が家を継がせる為、母里から養子の「長太郎」、12歳。
三女の「とく」、8歳。
そして初男子の「初五郎」、6歳。
太郎兵衛の女房と女房の実母(子供達には、祖母にあたる)の2人が、太郎兵衛の処遇の話しているのを、長女いちが盗み聞きしていた。
いちは夜中に考えた。
考えた挙句、嘆願書を書き奉行所にもっていけば父は助命されるかもしれないと思い、嘆願書を認(したた)めた。
夜中に何度も書き直し、清書し直した末、漸く出来上がった。
二女のまつが気づき、一緒に行く約束をした。
途中でまつが寝付いていた為、まつを起こし、いちは出かけようとした。
いちとまつが出かけようとすると、養子の長太郎が起きた。
いちの話を聞き、長太郎も一緒に行くと言い出したので、一緒に連れて行く事にした。
3人はまだ朝早いうちに、今月の当番奉行の西町奉行「佐佐又四郎成意」の処に急いだ。
西町奉行所に着いたが、まだ開門前。
3人は門番に取次を頼んだが、文字通り門前払いを喰らう。
しかし此処で諦めてはお終いと、3人は正式な開門まで待った。
開門時間になり門が開くと、3人は堂々と中に入り嘆願書を渡しに行こうとした。
あまりも堂々とした行動だったので、門番が呆気にとられた程だった。
漸く呼び止められ、そうこうしている中、騒ぎが大きくなり色々な役人が集まってきた。
そこを見計らったかのように、いちは懐中から嘆願書を差し出した。
役人達はどうして良いやら分からず、与力は一旦嘆願書を預かった。
古今東西、役人と言う者は「自分の権限で判断しかねるもの」であれば、一旦預かり、上からの指示を仰ぐのは何処の世界も同じ。
しかし此れは役人に限らず、民間も同じ。
下手に自分の裁量で判断した後、失敗でもすれば、その責任を問われかねない為。
佐佐は事の次第を与力から聞き、城代「太田備中守資晴」と東町奉行「稲垣淡路守種信」に相談した。
一応、目安箱もある手前(前述したが、この時は吉宗の治世)、預かったのであれば、目を通そうとの算段であろうか。
もし当時の目安箱の制度がなければ、いちの嘆願書はおそらく無視されていたに違いない。
3人が嘆願書をみた結果、拙い文字だがなかなか上手く纏めてあるとの結論に至り、奉行所では直接預かれない為、手筈を整え順序立てて申し立てよとの沙汰を下した。
これも役人体質を良く示している。
俗に言う「形式主義、たらい回し」の類。此の時代はハンコは無いが、ハンコ主義等の典型。
結局、奉行所は町年寄の5人衆経由として、嘆願書を受け取る事にした。
翌日、桂屋太郎兵衛一家は、西町奉行所のお白洲に呼び出された。
白洲前の書院には、佐佐・稲垣の両奉行、表に出てないが、隠れて城代太田備中守がいた。
話の成り行きを聞こうしたのである。
調べは年齢順に行われた。初めは女房。
女房は奉行の尋問にしどろもどろに答えたのみ。全く知らぬ存ぜぬで、要領を得ない。
次は長女いち。
いちは今までの経緯を臆することなく、一部始終を話した。
嘆願書に相違ない事、昨日の行為は誰にも相談する事なく、私とまつで決めたと断言した。
次は、二女まつと長太郎。
長太郎は昨日は嘆願書の内容が分からず、自分のみ助命してくれとの内容が含まれていた為(長太郎は養子だった)、新たに自分も養父の命と引き換えにして頂きたいとの嘆願書を作成。お上に提出した。
次は、とくと初五郎。
とくは、どうして此処に来たのかも分からない年齢。ただ泣いているだけ。
初五郎は、お上に「死ねるか」と聞かれた際、正直に首を横にふった。
一同は初めて子供らしい姿を見た気がしたのか、思わず笑った。
此れが元来の、子供らしい反応と誰もが思ったのであろう。
佐佐は「誰かの入れ知恵、差しがねではないか」と、改めていちに問うた。
するといちは少し間を置き、何を思ったのか咄嗟に
佐佐は思わず「呆気に取られたと言うべきか、してやられた」と言う気持ちに捉われた。
その場に居た役人誰もが、そう思ったに相違ない。「寸鉄人を殺す」とでも云うべきか。
それ以降、煙たいものでも見たかの様に、太郎兵衛一家は白洲から立ち退かされ、お裁きは終了となった。
裁きの後、佐佐・稲垣・太田の3人は言葉は従順だが、「役所の体質を皮肉る」いちの態度に嫌悪感を抱いた。
いちの嘆願が功を奏したかどうかは分からないが、慶事があり恩赦の名目で太郎兵衛は死罪は免れ、処払いのみの軽い刑に減刑された。
追記
「最後の一句」は私が中学生、国語の授業で学んだ教材。
当時の年齢では時代背景・社会機構等が分からず、理解しがたい作品だった。
大学卒業後に社会人になった際、漸く納得できた。組織と個人との関係と距離、上からの命令等。
特に公的機関に対する個人との関係を、色々と考えさせられた作品だったと言える。
作者鴎外はご存じの通り、明治政府の役人。バリバリの官僚組織の一員。
しかも当時一番厳しいと言われた、帝国陸軍の軍医だった。人一倍、官僚組織を熟知していたであろう。
鴎外が官僚組織の一員であり乍ら、組織を皮肉った作品を描いているが何とも興味深い。
本人も膠着した組織に対し、何か疑問を呈するモノがあったのだろうか。
尚、戦後軍隊(陸軍は解体、海軍組織はそのまま残った)は一旦解体したが、官僚機構はそのまま残り、現在に至る。
今日の日本社会では、様々な問題が生じている。中には組織が疲労を起こし、その歪が表面化されたものが多く存在する。
何れにせよ物事の本質は、今も昔も殆ど変わらないと言う事なのかもしれない。
(文中敬称略)
他の森鴎外作品
◆見知らぬ物に対する盲目の尊敬と権威主義。森鴎外『寒山拾得』