地獄から抜け出す寸前、醜い心が招いた結果 芥川龍之介『蜘蛛の糸』
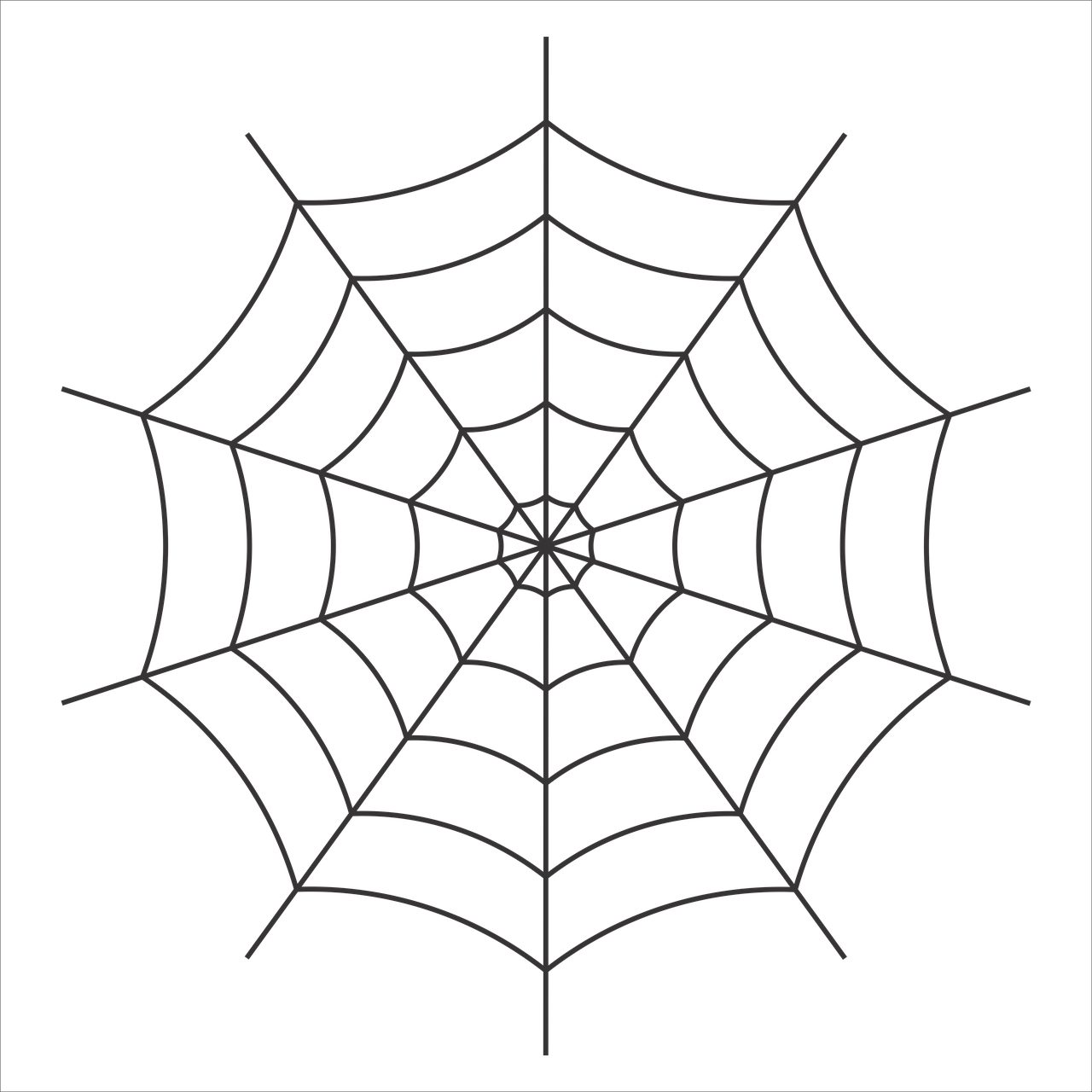
★芥川龍之介短編小説シリーズ
・題名 『蜘蛛の糸』
・新潮社 新潮文庫 『蜘蛛の糸・杜子春』内
・発行 昭和43年 11月
・発表 大正 7年 7月 『赤い鳥』
目次
登場人物
◆犍陀多
生前、様々な悪い事をして人に迷惑をかけた罪人。
生前の報いを受け、当然の如く地獄に落とされる。
地獄で責め苦を受ける。生前散々な悪さをした犍陀多だが、たった一つ善い事した。
その善行により御釈迦様のご加護で、地獄から救い出されようとするが。
◆御釈迦様
極楽に住む仏教の聖人。
蓮池の淵を散歩していた際、偶々地獄に落とされた犍陀多を見つける。
御釈迦様をふとした気紛れで生前、犍陀多がたった一つ善い事をしたのを思い出し、犍陀多を地獄から救おうとするが。
あらすじ
生前悪さばかりしてきた犍陀多だったが、その犍陀多もたった一つ善い事をした。
目の前に現れた蜘蛛を踏みつぶそうとしたが、その時は何故か蜘蛛を憐れむ気持ちが湧き、蜘蛛を逃がした事だった。
生前の悪行で当然の如く地に突き落とされ、地獄の責め苦を受けていた犍陀多だったが、極楽の御釈迦様は何を思ったのか犍陀多のたった一つの善行を思い出し、犍陀多を地獄から救おうとした。
幸い近くの蓮の葉の上に蜘蛛が一匹、佇んでいた。
御釈迦様は蜘蛛を掴むと、蜘蛛の糸を犍陀多がいる地獄の底に垂らした。
一方、地獄の血の池で地獄の責め苦を受けていた犍陀多の前に、一本の糸が垂れ下がってきた。
犍陀多は思わず糸を掴み、上に昇り始めた。
不思議な事に糸は何処まで昇っても、切れる様子はない。
犍陀多は此れで地獄から脱出できると喜び、益々上に昇った。
どれぐらい昇ったであろうか。流石の犍陀多も疲れを感じ、糸を手にしながら一休みした。
犍陀多が休み乍ふと下を見下ろせば、先程自分がいた血の地獄から抜け出そうとする何千人もの罪人が、自分と同じように蜘蛛の糸を昇りは始めている様子が伺えた。
その様子を見た犍陀多は、此処まで昇ってきた努力が水泡に帰すと思い、思わず叫んだ。
「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己のものだぞ。お前たちは一体誰に尋いて、のぼって来た。下りろ。下りろ」と。
芥川龍之介『蜘蛛の糸』から引用
犍陀多がその言葉を発した途端、犍陀多のぶら下がっている処から糸がプッツリと切れてしまった。
糸が切れてしまい犍陀多は又もとの地獄に落ちてしまった。
折角お釈迦様が生前たった一つの善行により、犍陀多を地獄から救おうとしたが、犍陀多の自分たけ助かればよいという身勝手で無慈悲な心が、再び犍陀多を地獄に突き落としてしまった結果となった。
正しく因果応報、自業自得とでも謂おうか。
御釈迦様の慈悲も、犍陀多には全く無駄だったようだ。
要点
作品が発表されたのが、大正7(1918)年の為、当時の尋常小学校などでは「修身」と云われる授業が行われていた。
修身の授業とは、私の時代に存在した「道徳」の授業ようなものと思われる。
当時の時代を鑑みれば、道徳より更に厳しい内容だったと想像される。
その様な時代の作品の為、当然「信賞必罰」の観念が強い時代だった。
作品内容も、ほぼ単純明快。生前悪い事をした人間が死後、当然の如く地獄に落とされる。
地獄で責めにあっていた犍陀多を、偶々一度だけよい事をしたというお釈迦様の気紛れで、犍陀多を地獄から救おうとした。
丁度近くに生前犍陀多が命を救った時と同様、一匹の蜘蛛がいた。
御釈迦様は犍陀多を地獄から救おうと蜘蛛の糸を垂らすが、自分だけ助かればよいと欲をかいた犍陀多は、御釈迦様の怒りを買い、又もとの地獄に落ちてしまうという話。
当に
という、人生の戒めのような作品。
私を含め、皆様にも心当たりがあるかと思う。
子供の頃、作品を読んだ際、地獄に落ちた犍陀多を言葉は悪いが「ざまぁみろ」と思った。
しかし大人になり再び作品を読み返せば、何か犍陀多の事を「ざまぁみろ」と思えなくなった。
何故かと言えば、人間大人になれば何かしら一つや二つ、人に言えない秘密を抱える。
それが何年も経てば秘密が多くなる。人に拠り、罪悪感が増す人。
逆に麻痺してしまい、薄れる人もいるかと思う。
酸いも甘いも両方を噛分けるのが、大人になる事なのかもしれない。
そう思い乍、作品を読み返した。
昔絵本、TVアニメ等で一度は目に触れた方も多いと思う。それ程、有名な話。
果たしてあなたはどちらでしょうか。罪悪感が増す人。それとも徐々に薄れていく人。
人間生きていく上で果たしどちらが良いとは、決して一概には言えないと感じる自分がいる事に、改めて気づかされた。
(文中敬称略)