巧妙に絡めとられる役人 松本清張『弱味』
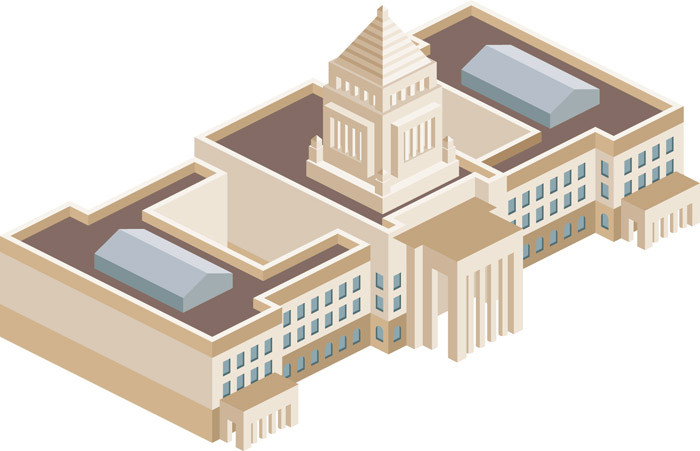
世間を暫し騒がす、役人の汚職、公共事業の官製談合など。
理由は様々だろうが、今回或る出来事を切っ掛けに、地獄に落ちていく役人の姿を描いた作品を述べたい。
・題名 『弱味』
・新潮社 新潮文庫
・或る「小倉日記」伝 傑作短編集(一)
・発行 昭和40年 6月
・原作 松本清張
目次
登場人物
◆北沢嘉六 :R市の都市計画に勤める課長。
◆志奈子 :北沢嘉六の愛人。嘉六とは20歳以上も違う。
◆志奈子の母 :志奈子の母。娘が嘉六の愛人であるのを公認。
◆赤堀茂作 :R市の市議会議員。
◆助役 :嘉六が勤めるR市の助役。次の市長選挙で出馬を目論む。
◆悪徳土建業者:赤堀がとつるむ土建屋。嘉六を使い、一儲けを企む。
作品概要
北沢嘉六はR市の市役所に勤める、都市計画課の課長。
愛人の機嫌とる為、愛人を伴い温泉に宿泊した。
嘉六は48歳、愛人の志奈子は20歳年下、28歳だった。
愛人は以前飲み屋勤めだったが、客だった嘉六と良い仲になり、嘉六から手当を貰う事で勤めを辞めた。
志奈子の家は、潮の香が漂う漁師の家だった。志奈子は父を亡くし、母と2人暮らし。
その為志奈子が勤めに出ていたが、嘉六が志奈子が勤めにでるのを好まず、家にいるのを望んだ。
母親も、嘉六との関係は公認だった。
志奈子は愛人だったが、嘉六の役所務めの手当では所詮、高が知れていた。
その為、志奈子親子の暮らしは決して楽ではなかった。
嘉六は志奈子の機嫌とりの為、志奈子を温泉に連れ出した。
夜になり2人は寝静まったが、嘉六は夜中に目が覚めた。
目が覚めた時、自分の部屋に泥棒が入り、金品・衣服類が一切盗まれているのに気付いた。
嘉六は一瞬、身の破滅が頭を過った。
しかし人間は窮地になれば、不思議と何かしらの悪知恵が働くもの。
普段仕事で何気に便宜を図っていた、市議会議員の赤堀茂作に電話した。
嘉六は赤堀に宿の支払い、替わりの衣服を持って来させるのに成功した。
今迄の恩義もあり、赤堀自身も普段から男気を気取っていた為、嘉六はすっかり窮地を脱したと安心していた。
しかしそれは、蟻地獄に落ちる入口だった。
後日、赤堀から嘉六に呼び出しがあった。嘉六は赤堀の呼び出された料亭に行った。
赤堀の狙いは、完全に「利益供与の要求」。
赤堀は違法建築の廃工場を公園建設に託け(かまかけ)、法外な値段で市に買い取らせる目論見だった。
嘉六は金額があまりにも法外な値段である事。
更に市は違法建築には一切お金を払わない事を知っていたが、嘉六は書類を無理やり改竄。
赤堀の要求の半分を渡す事を約束した。
手品のカラクリは、次の選挙で現助役が市長選に出馬する為、現在市役所内で自分の勢力を拡大している真っ只中。
助役は職員間の人気取りの為、書類の中味をあまり深く吟味せず、ただ認印のハンコを押していた。
嘉六は助役の政治工作を、巧みに利用した。
書類を巧妙に改竄。市長の留守時を見計らい、助役に偽造書類を提出。
認印を貰う事に成功した。
嘉六は赤堀の法外な要求額の半分を、市の公金から出させる事に成功した。
嘉六は此れで、温泉宿での借りが返せたと思った。
或る日、又も赤堀から嘉六に呼び出しがあった。
例の如く料亭で談笑後、嘉六は赤堀から無理やり贈り物を渡された。
贈り物とは、借家だが瀟洒な一軒家。
さりげなく赤堀が呟いた。此処に愛人の親子を住まわせては如何でしょうかと。
赤堀は温泉宿では志奈子には会っていなかったが、こっそり尾行でもしていたのだろうか。
ちゃんと嘉六の愛人が、志奈子である事を突き止めていた。
もう逃れる術はない。赤堀は嘉六を、骨までしゃぶろうとする魂胆。既に一連托生。
何も知らない志奈子親子は、もう潮の香が漂う、みずぼらしい家に住まなくてもよいと大はしゃぎ。
新居祝いでは、当然赤堀が呼ばれた。
当日赤堀は悪徳業者で有名な2人の土建屋を、お祝いと称し引き連れて来た。
祝いの席では愛人の志奈子は2人の関係など露知らず、ただ少女の様にはしゃぎまわっていた。
嘉六は赤堀から、悪徳業者の2人を紹介された。もう逃れる術はない。後は無間地獄の始まり。
地獄の終わりはどちらかが死ぬか、汚職が発覚するまで永遠に続く。
まとめ
暫し世間を騒がす、役人の汚職。
報道を聞いた時、何故悪いと分かっていながら、悪事に手を染めるのかと不思議に感ずる。
ほんの些細な出来事がきっかけで始まることが多い。
作品は市役所に勤める課長が、愛人と温泉宿に投宿。盗難にあう。
嘉六の場合、不倫・発覚を恐れての隠蔽の為、弁解の余地はない。
嘉六は助けを、市議の赤堀に頼んだ。
似たような事例で簡単に弱味を握られ、他人に絡め取られてしまう事象がある。
公務員の警官も同じ。
ふとした行為・不注意・魔が差した行為で相手に弱味を握られ、弱い立場に追い込まれ、相手に便宜を図ってしまう事例。
身近な例を挙げれば、盆暮れ毎に、自分の許に品物が届く。
最初は安価だった為、軽い気持ちで受け取っていたが、次第に高級品となる。
その頃には、すっかり感覚が麻痺。
そして或る日突然、送り主から今迄送った物の借りを返してくれと要求される。
初歩的だが、何気に有効な手段と聞く。警官等によくある例。
送り主は匿名だが、実は敵対する非合法組織である場合が多い。
此れは相手方に買収される典型的パターン。
役所と云う処は、極めて閉鎖的な世界。
勤め始めて大きなミスをしなければ、定年まで働ける。
定年まで長い。狭い世界で定年まで、同じ人間とほぼ毎日のように顔を合わせる。
自ずと相手に詳しくなり、色々な恨み・妬みなどのドス黒い感情が芽生える。
息苦しい、ギスギスした関係になりがち。ある種の閉塞感とでも言おうか。
更に役所は、年功序列と減点主義が蔓延る社会。
人事もほぼ入社年次に因る、「トコロテン人事」が行われる。
部署に因り、書類次第で幾らでも予算が降りる。
清張は役所の杜撰な構造を描く事で、役所の仕組みを皮肉っている。
読書後、同じ役所の弊害を鋭く突いた1952年作:黒澤明映画『生きる』を思い出した。
互いの作品は、似たようなテーマ。
清張と黒澤明作品を見比べた時、意外に似たテーマ、観点で描かれた作品が多いのに気付く。
互いの観察力・洞察力を伴った鋭い批判であろうか。
それは決して大所高所から物を見つめるのではなく、一介の市井から見た「反骨精神」。
今回の作品は自分の弱味に付け込まれ、悪の手に絡め取られていく人間を描いている。
しかし決して他人事とは思えない。
いつ誰の身に降りかかってくるかもしれない出来事かもしれない。
(文中敬称略)