後があると思えば、油断が生じる 『徒然草』上巻 92段
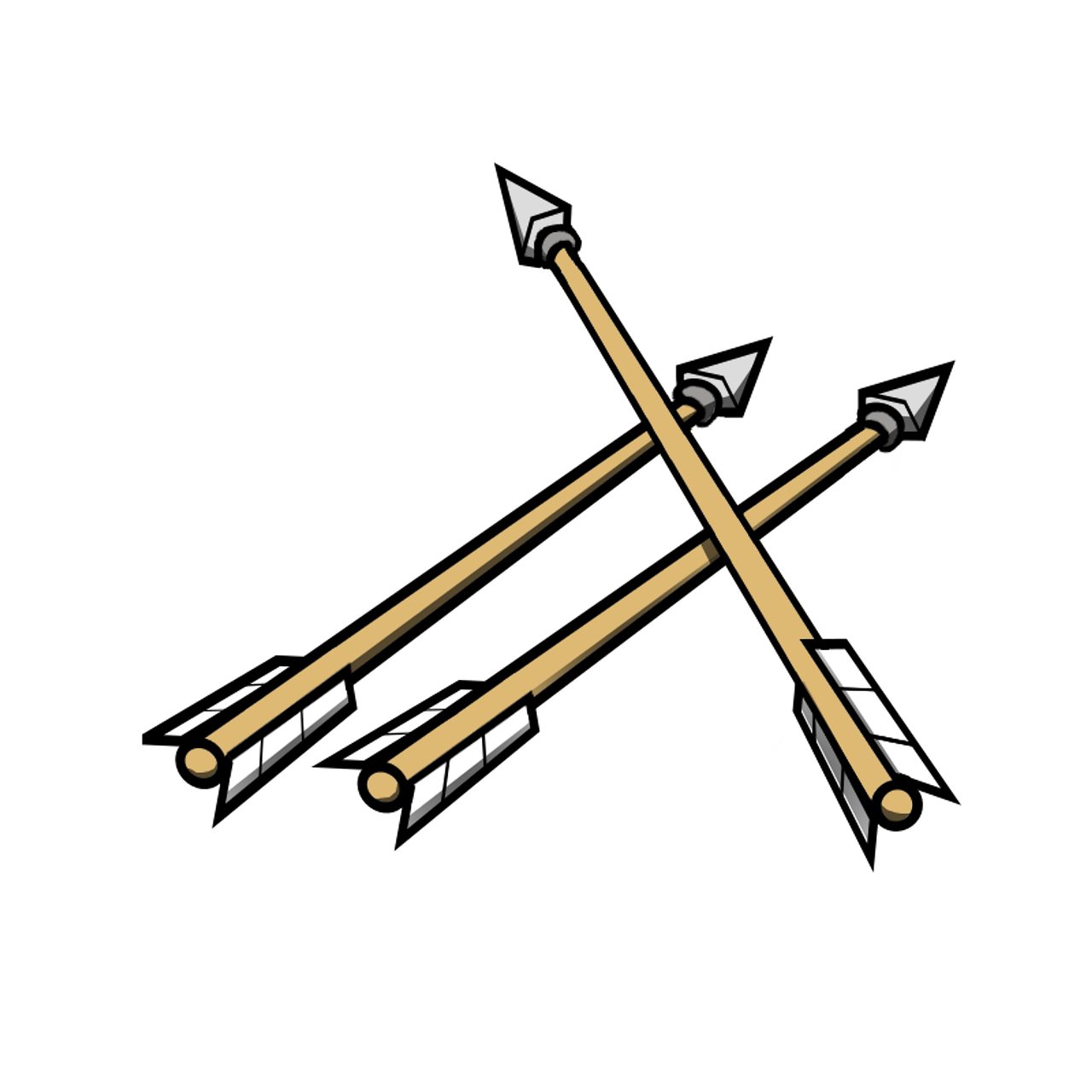
★今回は、「徒然草」の人生に於ける戒めとなる段を紹介します。
・出典元 『徒然草』
・上巻 第九十二 引用
・出だし 或る人、弓射る事を習うに、
目次
◆原文
或人、弓射る事を習ふに、諸矢をたばさみて的に向ふ。師の曰く、「初心の人、二つ矢をもつことなかれ。後の矢をたのみて、始めの矢になほざりの心あり。
毎度ただ後の矢なく、この一矢に定めるべしと思へ。」といふ。
わづかに二つの矢、師の前にて一つおろそかにせんと思はんや。解怠の心、自ら知らずといへども、師これを知る。
この戒万事にわたるべし。道を学する人、夕には朝あらんことを思ひ、朝には夕あらんことを思ひて、重ねてねんごろに修せんこと期す。
いはんや一刹那のうちにおいて、解怠の心あること知らんや。なんぞただ今の一念に於いて、することの、直ちに用ひること甚だ難き。
<参考>
・懈怠の心 なまけ心
・朝 明日の事。漢文では朝(あした)と呼ぶ。
◆現代語訳
或る人が弓矢を師匠から学ぶに、二本の矢を手に持ち、的に向かった。師匠がいうには
「初心者の頃は、矢を二本持ってはいけない。
何故なら、二本目を頼んでしまい、一本目を疎かにしてしまう。毎回二本目はなく、一本しかないと思って的を当てる心算で射よ」と述べた。
僅か二本の矢であるが、師匠の前では決して一本目を疎かにしようとは思わないであろう。
怠けの心は、自分では気づかないが、師匠は此れをしっていた。
この戒めは色々な事にも、当て嵌まると云える。修行をする人は、夕方には明日があると思い、明日には夕方があると思い、後で又しようと思ってしまい、つい丁寧に修行をする事をしない。
まして一瞬の中で、怠け心があろうとは、気づきもしない。
どうして今その瞬間に、やるべき事を直ぐにやるのが、難しい事であろうか。
◆要点
今回の段はあまり難しい文字もなく、ほぼ現代文の感覚でも読めるのではないだろうか。
つまり次があると思うから怠け心が生じ、初めにやる時、油断が生じて失敗するという戒め。
次があるからといって、今を疎かにしてはいけないという戒めも含むであろう。
兼好法師は此の戒めは万事に当てはまると述べているが、まさにその通りであろう。次があるから大丈夫と思っていると、大概次も失敗してしまう。
此れは自分にも当てはまる。過去に仕出かした失敗を検証すれば、大概この戒めが当て嵌まっている事が多い。
中には経験不足と云う事もあるが、逆に慣れが基で油断が生じ、失敗した事も多い。
それは文中にもある、「懈怠の心」というべきかもしれない。失敗をしでかす事に、絶えず今回の話を思い出し、自らの反省としている。
◆追記
何か此の話は、身につまされる話だった。
私は大学受験の時、一度失敗している。つまり一浪後、漸く大学に進学できたという過去を持つ。
決して油断していたという訳ではないが、自分で気づかない心の何処かに、隙があったのだろう。一年目は見事に失敗した。
失敗後、一念発起して再び受験に臨んだ。ほぼ一年の味気ない浪人生活を過ごし、一年後に臨んだ受験だが、此処でも過ちを犯した。
今にして思えば、此れも油断だったのかもしれない。失敗の内容を大まかに説明すれば、大学を6校受けたが、合格したのは、たったの2校だけだった。
その2校も本命ではなく、何れも滑り留め。
更にオチを付ければ、受かった2校は最初と次に受けた大学で、後から受けた4校は全て不合格。
此れは何を意味しているのか。
少し今回の内容と逆になるのかもしれないが、最初に受けた2校の出来栄えが善かった為、後の4校で気を抜いてしまい、不合格になったのではないかと私なりに推測した。
受験した経験があれば分かると思うが、試験後に合格か不合格かは、たいがい自分で判断できる。
私の場合、最初の2校の出来が善かった為、つい安心してしまった。
安心した為、後の4校に身が入らなかった。
結果もまさに、その通りだった。
皆様の中では、「2校受かったから善いのではないか」と仰る方がいるかもしれません。
確かにそうですが、繰り返しますが、本命は後の4校だった為、私としては失敗したと言えます。
やはり油断が生じた失敗。
話の内容は「後があると思い最初を疎かにしがちだ」というオチですが、私の場合は最初が上手く行き過ぎた為、後が失敗したという、何とも言えないオチになりました。
その事が幾年経っても、悔やまれます。
人生に「もし」はないが、もし当時に「僅かばかりの注意力があれば」、後の人生が変わっていたかもしれません。
そう思いながら、此の年まで生きてきました。果たして、どちらが正解だったのでしょうか。
(文中敬称略)