引き取り手のない遺体、全国で約4万2千人。厚労省の調べに因れば
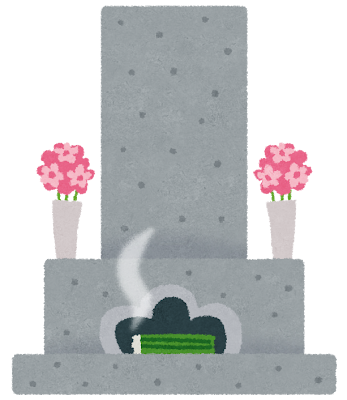
先日、気になるニュースを見かけた。
亡くなった方の引き取り手のない遺体が、約4万2千人との事。
データー基は、2年前の2023年、厚生労働省。何故、目に留まったのか。
それは私が、その予備軍の為。今回は、身につまされるような話題をしたいと思います。
目次
引き取り手のない遺体
厚生労働省の調べによると、2023年、全国で引き取りてのない遺体が約4万2千人との報告。
多い少ないか別として、ざっくり月平均約3500人。
各地域人口の格差がある為、一概には言えないが、1日平均約115人と云う事になります。
毎日どこかの都道府県で、2人以上が対象になると云う事です。
記事中にも触れていたが、1人暮らしの増加、身寄りのない高齢者が増加し、将来的な対策が必要だとの事。
将来的には、増加の見込み
前章では、身寄りのない高齢者が増えたという分析。
分析はその通りだと思う。今後益々増加するのも事実。
理由は、私が何時も述べている様に、
団塊二世で就職氷河期を経験した世代が20年後、全員が年金受給者となる為 。
繰り返すが、この世代が就職に躓き、非正社員の割合が高く、貯蓄と年金の積み上げが少ない世代。
そして最も、世代間が多い世代。この世代が年金受給となる頃、年金の財源はないと予測する。
年金の話は今回の引き取り手のない遺体とは少し異なるが、後で関係する為、此処までにしたい。
重要なのは、非正社員で経済的に恵まれなかったからであろうか。未婚率が男女間で高い。
具体的には、 男性約30%。女性約20%。大まかに男性は、3人に1人。女性は、5人に1人が独身 。
今後結婚する可能性もあるが、子の誕生は難しい。因って何方かが無くなれば、身寄りがない事になる。
50才同士で結婚しても、将来的に身寄りがいないのは、ほぼ間違いない。
では、引き取り手のない遺体は
自宅や病院で亡くなり、身寄りや相続人がいない場合、墓地埋葬法に基づき死亡した市町村の自治体が引き取り保管。火葬か土葬を行う。
極端な話、もし国内の旅先で死亡。引き取り手がない遺体は、その旅先の自治体が処理しなければならない。
一応、親族に確認を取るが、大概疎遠の為、 そちらで処理して下さい との返答が多い。
因って死亡した人は、人生の最終地で火葬か埋葬され、共同墓地で無縁仏となる。
此れが世界でも有数な福祉国家と云われ、高い社会保障費を払った、老後の末路。
果たして皆様は、どう思われたでしょうか。
安楽死と、今回の記事は異なる
ニュース後の書き込みを見た時、色々な書き込みが見られたが、一部でおやっと思うコメントがあった。
それは、安楽死についてのコメント。
内容は安楽死の検討と導入について。コメントに対し、賛同する意見も多く見られた。
私もコメントを読み、一瞬成程と思ったが冷静に考えた際、少し論点がズレているのに気づいた。
何故なら、安楽死と引き取り手のない遺体は、意味が違う為。
敢えて反論すれば、譬え安楽死を選択をする、しないに係わらず、引き取り手の有無は変わらない。
つまり人が無くなっても、引き取り手がいるのかいないのかは、その人の家庭事情による。
天涯孤独の人であれば仕方がないが、もし遺族が引き取りを拒否すればそれまで。
遺族がいても同居していなければ、拒否する事も可能。
何故、安楽死の話が出たのか。
私は甚だ穿った見方をするが、此れは将来の布石だと思う。
将来の布石とは、ズバリ年金受給者を減らす為の方便。
過去の私のブログを見た方であれば、分かって頂けると思います。
今の社会構造の歪は、全て団塊二世で就職氷河期世代が原因。
此れも何度も述べてますが、現在日本が抱える全ての問題は此処に起因します。
少子高齢化の原因も全て、この世代が原因。
団塊二世で就職氷河期世代が、最も世代間が多かった。その世代が約20年後、全員年金受給者となる。
年金が支給される頃、おそらく財源はないでしょう。その為、少しでも受給者を減らそうとする詭弁に使われる可能性がある。
何故そう言い切れるか。それは以前から述べている様に、
私が団塊二世で就職氷河期を経験し、私が孤独死の予備軍の為 。そう考えた時、今回の記事は何か身につまされるような話だった。
(文中敬称略)