政治とは所詮、「エゴの調整」に過ぎない。
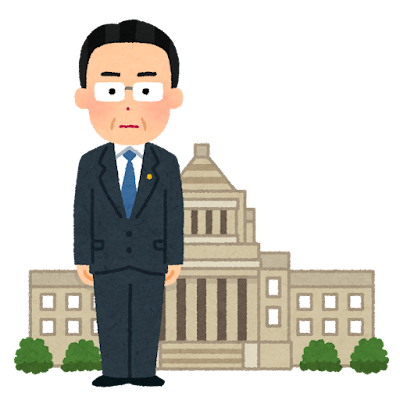
今迄、政治について政策を論じた事は度々あったが、政治全般について述べた事はなかった。今回は政治全般について述べたい。
目次
政治とは突き詰めれば
いきなりタイトルで結論を述べたが、政治とはつまり、「人のエゴの調整」のようなもの。
どれだけ綺麗ごとを並べても、それ以上それ以下でもない。それに尽きる。
しかしそれが分かるまで私は、かなりの時間を要した。時間を要したのは、それをはっきり断言できるまでと言い換えても良いだろう。
私の時代は選挙権が満20才になり、国から自動的に付与された。
当時を振り返れども、何が何だか分からなく、ただ選挙権が与えられたとしか記憶していない。
当然、政治の事や政党政策など、皆無に等しかった。唯一、政治に触れたとすれば、就職試験で時事問題が必要な為、僅かながら勉強したぐらいであろうか。
本当に、そんな程度だった。
私が初めて選挙権を行使した時
更に私は20才の頃、進学で上京。住民票を移していなかった為、選挙権は生まれ育った田舎にあった。
その為、投票する意識や政治に関する興味など、殆どなかったと云ってよい。
大学卒業後、初めに就職した会社にて新潟支店勤務を命じられ、社会人を一歩を踏み出したのも他県だった為、選挙権を行使することはなかった。
実際に私が初めて選挙権を行使したのは、初めて就職した会社を退職。赴任先(新潟)から戻った時。
初めて就職した企業を退職後、私は故郷に戻り暫く休養。心身共に回復し、次の就職先を探している最中だったと記憶している。
初めて投票した国政選挙
私が初めて選挙権を行使したのは、1990年代の国政選挙だった。
1990年代は戦後長い間政権与党を担っていた自民党が下野した年代。その頃は与党だった自民党が分裂。
自民党を飛び出した議員が新党を作り万年野党だった政党と連立。連立政党により、与党だった自民党の数を上回り政権を奪取した。
しかしその政権も1年も持たず崩壊。あろうことか、当時連立与党にいた旧社会党が連立を離脱。
そのまま一時的に野党だった自民党と連携。更に当時のさきがけも抱き込み、「自・社・さ」連立が成立。
その後、再び自民党は政権与党に返り咲いた時代だった。
議員達は政権闘争に明け暮れた。その間、国民はおき去りにされた。
その結果が今日にまで続く日本の停滞を招いたと云っても過言でない。
そんな政治が混乱、バブル経済が崩壊と殺伐とした1990年だったと記憶している。
前述したが私は当時20代で、学生から社会人へとなる過程。当時の社会状況をもろに受けた世代。
一度でも私のブログを読んだ事のある方であれば、お分かりだと思う。
この世代がバブル崩壊のあおりを受け、そのままズルズルと日本経済停滞の渦に巻き込まれ、そのまま今日に至る。
まさに何も社会の恩恵を受けず、その後ITバブル崩壊、リーマン・ショック、コロナ騒動を経験。確実に、人生で貧乏くじを引き続けた世代。
長々と当時の世相を説明したのには訳がある。
その訳とはつまり、前述したように私の世代は人生の於いて政治や社会の恩恵を全く受けずそのまま歳を取り、今では働き世代と云われる年齢を終えようとしている。
私たちの世代がバブル経済崩壊後の日本を、そのまま象徴している。
バブル経済が崩壊して約30年以上経とうとしているが、日本人の年収は当時の水準か減少しているのが現実。
その間、他国は毎年経済発展が進み、今では時給換算では日本はカナダ・オーストラリアの約半分となった。
如何に経済発展が分かる事象と云えるだろう。そんな日本の状況下で私たち世代、少なくとも私は政治や社会に全く期待していない。
期待していないどころか、ややもすれば不信感すら漂う。理由は既に述べた通り。
自ずと投票行為に対し、シビアにならざるを得ない。
選挙とは将来の日本、自分の未来に期待を込め投票する行為だと私は思う。
しかし今迄私が投票した目的は、大概前回投票した党、或いは人物とは異なる行為だったと感じる。
つまり前回期待して投票したが裏切られたと感じ、次は反対票を投じたとう意味を表す。
前回期待した分の反動と思えばわかり易い。それだけ私は選挙の度に絶望感と悲壮感にとらわれた。
当選する候補者は所謂、世襲か族議員
何度か選挙を経験した人であれば分かるが、選挙で当選する人物は大概、ある特定の利益団体が推薦する人物。
或いは、代々その地盤で何代から続く一家がたえず当選しているのではないだろうか。
特に後者は、田舎であればあるほど如実。
昔の幕藩体制がそのまま続いているのではないかと錯覚するほど。例を挙げれば枚挙に暇がない。
それほど日本の選挙は、政治家は世襲ともいえる現象が根強い。
話は前後するが、最初に述べた族議員とは今更説明するまでもないが一応簡単に述べれば、
「様々な利益団体・圧力団体が存在するが、その団体の利益を守る為に存在する議員」と云って良いだろう。
つまり議員になる人物は、その団体の為に働くのが目的ということ。
その為、団体に不利益になる行為はしないのが当たり前。それが俗にいう、「組織票」と云われる大きな票に繋がる。
大票田とも云える。現在の選挙では、この組織票の影響が大きい。
特に組織票は投票率が低ければ低い程、選挙の行方を大きく左右する。
繰り返すが、大方当選する候補者は、この二者に該当すると思われる。
ややもすれば、両方を兼ね添えている人物が議員であることが多い。
読者の皆さんも、一度自分が住む議員(国会、県議会、市議会、町議会)を見渡せば、何方かに該当する筈。
此れが日本の選挙の大きな特徴。
県議会、市議会、町議員クラスであれば、数名の無所属議員もいるが、他の多くの議員は何かしら政党に所属している。
此れが国民の選挙の無関心、投票率の低さの原因の一つ。
つまり自分が良いと思う候補者が、なかなか当選しない。
当選しない為、徐々に政治に関心が薄くなり、結果投票しなくなると云った悪循環に陥っている。
毎週、日本各地で何かしら選挙が実施されているが、投票率が50%を超えれば投票率が高かったと云われる。
如何に国民が選挙に関心がないかの証左とも云える。
昨秋と今夏の国政選挙にて
処が今迄国民が選挙に関しあまり興味がなかったが、昨秋行われた衆議院選挙、又今夏行われた参議院選挙では面白い現象が起こった。
先ず昨年秋の衆議院選挙では、調査が行われて2番目に投票率が低かったにもかかわらず、政権与党(自公)が過半数割れを起こした。
その現象は今年の夏行われた参議院選挙でも見受けられた。参議院選挙では選挙投票日が3連休の中日だったにも関わらず、なかなかの投票率だった。
なかなかと云っても、約56%ほどだったと記憶しているが。それでも政権与党は大幅に議席を減らし、野党が議席を獲得した。
野党と云っても満遍なく分散されたわけでなく、特定の野党が躍進とも云える票と議席を獲得した。
これを簡単に分析すれば、戦後ほぼ政権を担ってきた自民党に対し、国民が「ノー」を突きつけた結果。
特に昨秋の衆議院選挙は、投票率が低かったにも係わらず組織票の強みを生かせなかったのは、かなり危うい兆候。
組織票の中に、かなりの造反者がいたとも云えるだろう。それだけ国民は今の生活に不満を抱いている。
漸く国民が政治に目覚め、選挙により意思表示をする行為をしたと云える。
昨今の日本の社会事情を見れば当たり前であり、むしろ遅すぎたともいえる。
果たして総裁選の意義は
現在、自民党は次の総裁を決める為、選挙を実施している。
今まさにこのブログを書いている最中、総裁選が行われている。
総裁選に立候補しているメンバーは5名。そのメンバーを詳らかに眺めれば、なんのことはない。
去年、同時期に行われた総裁選のメンバーとほぼ同じ。
要するに、去年行われた総裁選が又繰り返されたということ。
結論を述べれば、去年行われた総裁選は無駄だったということ。
つまり、日本という国は、一年を棒に振るったということ。
「時間」は人間で、一番大切な財産。つまり、貴重な時間を失ったということに他ならない。
これは何も今に始まったことではない。
何度も繰り返すが、これはバブル経済が崩壊した1990年代の政治の様相を国民は、そのまま見せつけられているに過ぎないということを物語っている。
理由は、前述した通り。
自民党内の「コップの中の争い」をという田舎芝居(茶番劇)を何度も見せつけられているに等しい。
これがそのまま、日本が停滞した原因。愚かにも日本という国は再び、その愚行を冒そうとしている。
一方、政権を監視する野党は
今回、政権与党の批判ばかりを繰り返してきたが、一方野党もまた似たような状況。
2009年の総選挙にて政権交代が行われたが、当時の政権は悪夢だった断言してもよい。
それ程、お粗末な政権運営だった。
それに懲りたのか当時政権だった野党は、積極的に政権を取りにいくという姿勢があまり感じられない。
少なくとも私には、そう見える。
何故なら、繰り返すが昨秋の総選挙にて政権与党が過半数割れを起こした。
その為、通常国会で内閣不信任決議案を提出すれば可決する可能性は十分あり得た。
しかしそれは実現しなかった。何故実現しなかったのか?
それは、 各野党の足並みが揃わなかった為 。
3月末の予算審議では、政権与党は野党の維新を抱き込み、予算案を通過させてしまった。
この時点で現内閣が倒閣する可能性がなくなった。
野党第一党である立憲民主もいつもであればお約束のように、通常国会で一度は内閣不信任案決議を提出するが、今回はしなかった。
何故しなかったのか。それは、もし提出すれば不信任案決議が通過する可能性があった為。
可笑しな話だが、絶対通過しない時に不信任案を提出し、通過する可能性がある時、提出しない。
これでは本気で政権を取りにいっていないと云われても仕方がない。
つまり万年野党の精神が染みつき、ややもすれば政権与党となり責任を担うより、ただ政権批判をすれば良いという気持ちが議員間で漂っている雰囲気すら伺える。
国民も薄々それに気づいたのであろうか。
今夏の参議院選挙では立憲民主は議席こそ選挙前とあまり変化はなかったが、総得票という点では、大幅に票数を減らした。
実質、負けに等しい。そんな結果だった。
他の老舗の野党も同じ。特に参院選では維新、共産、社民等の凋落が激しかった。
社民(旧社会党)は既に、歴史的役目を終えたと云える。
同じ参院選で躍進した国民民主、参政も議席こそ増やしたが、政権を担うという点で見れば、まだまだという感が拭えない。
躍進した国民民主党と参政党の課題は、如何に党首の「個人商店」から脱却できるかどうかが鍵。
結局最後は、国民の責任
色々私なりの政治に対する意見を述べたが、最後はやはり国民が政治に責任を持ち、監視しなければならない。
現代では多くの国が民主主義(選挙制度)を採用している。
ただそれ以上、それ以下でもない。
一時的だが、国民が選挙という手段を用い、自分の利益を代表してくれる人間を選んでいるに過ぎない。
自分の利益イコール、エゴと置き換えてもよいだろう。その為、選挙では自分のエゴを実現してくれる人間を選択する。
因ってタイトルの如く政治とは所詮、「人のエゴを調整する行為」と私が唱える所以。
エゴの調整の具体的な行為とは、つまり「予算の獲得」。
国民から徴収した国の税金を合法的に自分に投票してくれた人、或いは組織の為に獲得してくる行動と云える。
税金(予算)の獲得もさること乍ら、支持してくれた人の為に有利な法案を設立するのも、結果的に同じことに繋がる。
人間がエゴを主張しあえば、自ずと其処には衝突、軋轢が生じる。
予算獲得と同時に衝突と軋轢の緩和も政治家には大切な仕事。
実は予算獲得よりも、衝突と軋轢の処理が一番難しいかもしれない。
暫し政治家が恨みを買いテロに遭遇するのも、これが原因と云える。
ある特定の団体に有利な政治活動をすれば、必ずその反対に不利益を被る団体がいる。
団体に限らず、人も同じ。政治をする人間が命がけなのも分かるような気がする。
世の中、必ずしも100%満足なことはない。此れは断言できる。せいぜい賛成は40%あれば善いほう。
参考までに株式会社では株取得が約40%で、その会社の経営権を握れる。まさにそれと同じだろうか。
しかしどれだけ政治家が特定の組織集団の利益を代表する人間だとしても、やはり最後はその政策が国民の利益に叶うかどうかが肝要。
結局、政策の一つ一つを国民が監視しなければならない。
監視する為には国民の多くが政治に関心を持ち、自らの意思を示す為、投票しなければならない。
国政選挙が60%を超えないというのも、他国からみれば可笑しなことだと認識しなければならない。
過去のブログでも述べたが、第一次世界大戦後、最も民主的と云われたドイツでナチが誕生した。
その原因はいろいろあるが、一番の原因は国民の政治への監視が不十分だったことだと思う。
此れも以前何度も述べたが、政治は右も左も根は同じ。
民主主義だったが国民が監視を怠った結果が、ナチ政権を招いた。
旧ソ連のスターリンの独裁政権も同じ。それが私が右も左も同じ述べる所以。
古く歴史を遡れば、古代ギリシャも同様。歴史上、一番早く民主政治が誕生したギリシャは時代を重ねるごとに腐敗した。
貴族政治→僭主政治→民主政治と変遷したが、長続きはしなかった。民主政治は衆愚政治となり滅びた。
実は人類の歴史は絶えずこの繰り返し。
ギリシャに変わりローマが栄えたが、共和制を採用したローマもやがてシーザー(カエサル)のような独裁者を生んだ。
歴史と政治はまさに一体。古今東西、常に歴史と政治機構は両論の如く、シンクロナイズしている。
歴史は過去を繰り返しているに過ぎない。
そう思い現在の政治を眺めれば、自由選挙があるだけ、まだましと云える。
その「まし」と云える政治機構(民主主義)をできるだけ維持しなければならない。
現在の政治機構を維持する為には、やはり国民が政治に関心を持ち監視、意思表示の為に投票しなければならない。
昨秋から今夏の国政選挙の結果を経て、いま改めて政治を振り返れば、私は益々この気持ちを強くした。
(文中敬称略)